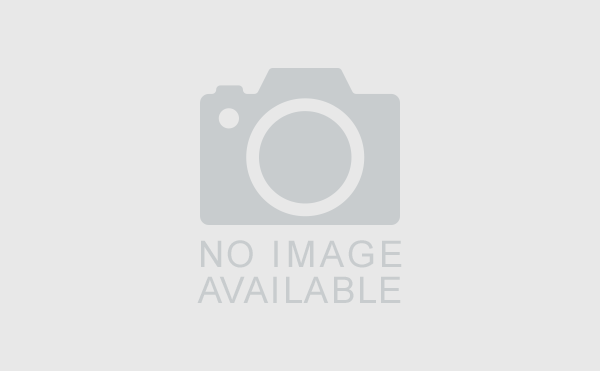梅酒に氷砂糖を使うわけ
唐突に。
梅酒になぜ氷砂糖を使うのかを丁寧に説明していきたいと思います。
キーワードは濃度勾配と浸透圧。
梅酒っていうのか簡単にいうと、梅のエキスが溶け込んだお酒です。
漬けるに当たっては発酵はせず、いわゆる抽出という作業が瓶の中で行われます。
抽出するには、一度水やアルコールを梅に含ませて梅のエキスを溶かしこみ、
のちにそのエキスを梅に吐き出させるという、真逆のプロセスを経る必要があります。
そのプロセスには”浸透圧”という現象を用います。
そして氷砂糖を使うことによって、一度吸わせて吐き出させるというプロセスを自動で行うことができます。
浸透圧とは、濃度差が異なる液体の間に、半透膜と呼ばれる溶媒(液体)のみが自由に行き来できる膜を置いたときにできる液の移動圧のことを示します。
通常、濃度の異なる液体が接すると、熱力学の法則に従い濃度が均一になるように混ざり合います。
一方で、半透膜を挟むと、溶質(砂糖や塩などの溶け込んでいるもの)は行き来できないため、なんとか濃度を均一にしようと、濃度の濃い液体に向かって、濃度の薄い液体から溶媒が流れ込みます。
例えば、お風呂に入って指がふやけるのは、お湯が指に向かって浸透しているからで、
野菜に塩をつけると、野菜の水が出てくるのは、野菜から塩に向かって水が浸透しているわけです。
どちらも濃度の薄い方から濃い方に行くというのがポイントです。
で、本題。
梅酒を漬けたばっかりの時。
お酒と梅とまだ溶けていない時の氷砂糖では、お酒成分が薄く、梅の果実中の濃度が濃いため、水とアルコールが梅の果実に向かって浸透していき、梅のみがふやけます。つまり梅がお酒を吸うわけです。
で、しばらくして氷砂糖が溶けてくると、今度はお酒の濃度が濃くなり、
先ほど吸った果実中の液が、梅エキスごとお酒の中に出されていきます。
こうして氷砂糖の溶ける時間差をうまく利用して、ワンポッドで浸透と抽出を行っているのです。

写真の解説ですが、瓶の上にはお酒を吸ってパンパンになっている梅があります。
瓶の底には溶けきらずに残っている氷砂糖があります。
つまりこの瓶の中は下に行くほど濃度が濃くなっています。
そして瓶の中間には、濃度の濃い部分に触れて、中身のエキスが搾り取られてシワシワになってしまった梅があります。
このシワシワの梅もつけた当初はパンパンになってたんですけどね。
つまりこの瓶はまさに抽出の真っ最中なわけです。
こうしてじわじわ濃度勾配が是正されて、上の方の梅もシワシワになったら飲み頃と考えていいんじゃないでしょうか。
梅酒一つとっても、なかなか合理的な先人の知恵が詰まっているわけですね。