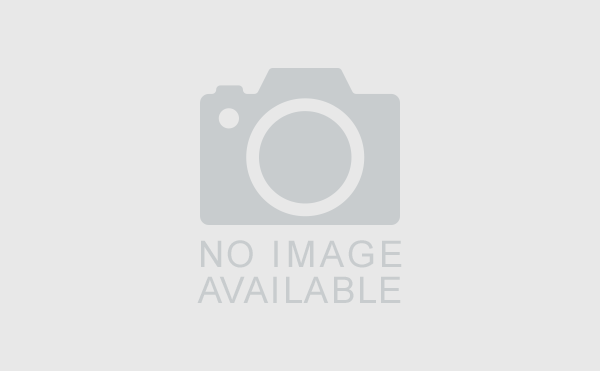患者のプライバシーにどこまで踏み込むか ~前編~
※1 あくまで個人的な思想であり、千葉大学でこのように教えているわけではありません。
※2 まだ学生であり、臨床の現場も知らない人間の意見です。来年には180°変わっている可能性もあります。
※3 HIVとはHuman immunodeficiency Virus(人免疫不全ウイルス)の略です。
※4 AIDSとはAcquired ImunoDeficiency symdrome(後天的免疫不全症候群)の略で、HIVにより免疫機能が低下したことから起こる感染症などの症状のことで、
人が亡くなるのはAIDSのせいです。
※5 HIV感染からAIDS発症までには一般的に約10年程度かかると言われ、薬を飲むことでHIVの増殖を抑え、AIDS発症を抑えることができます。
今回のIPEでの模擬患者の症例は妻子持ちのAIDSによるニューモシスチス肺炎であった。
HIV感染は現在では、1日に2錠の薬を欠かさずに飲むことができれば、もはやAIDS発症の可能性は限りなく低く、健常人となんら変わりない生活を送ることができる。
むしろ問題となりがちなのは、HIV感染が判明したのちの社会的活動をどれだけ継続できるかといった点であり、この症例も家族や職場への告知が主たる論点であった。
医師の仕事が「HIV陽性ですね。お薬1日2錠欠かさずに飲んでくださいね。では次の方。」で済ませられないのは、患者その人のフォローも大事だからだけでなく、周囲への感染拡大を防ぎ、また感染の可能性がある人を洗い出さねばらなないからである。
そこで今回の症例をモデルとし、医師としてどこまで患者のプライバシーに踏み込むべきかを考察した。
まずプライバシーとは何かを定義する。辞書によると大まかに、個人や家庭内の私事、個人に秘密とある。
特に、「秘密」の部分を噛み砕くと、知られたら「嫌」な情報であると考える。人によって同じ情報でも、それを知られて嫌と思うかどうかで、それがプライバシーに当たるかも変わってくる。
例えば、免許証の顔写真を見られることにまったく抵抗のない自分には、それはプライバシーになりえず、一方絶対見せたくない人にとってはプライバシーに該当する。
HIV感染の情報はほとんどすべての人が知られるのを嫌だと感じるので、これも当然プライバシーに該当する。
それではそのプライバシーに医師としてどこまで踏み込むべきか。思想の侵略が戦争の始まりをモットーとする個人的な考えの礎として、基本的には全く踏み込みたくないし、できれば踏み込まずに患者の希望に沿う形での治療の計画を立案したいと考えている。
それは個人的な思想だけにあらず、他人の思想を変えることは非常に困難であり、制限されたら嫌と感じ、治療計画が達成されない可能性が高いと考えるからである。
恐らく、恐らく1日の歯磨きの回数ですら制限されることに抵抗があるし、ましてや炭水化物が好きな糖尿病の患者に糖質制限をさせることや、HIV感染の原因となったような行為を本当にやめさせることは、患者本人が強い意志を持たない限り非常に困難なことが容易に想像できる。
そこに病気の原因となりうる明確なロジックが存在し、頭では理解していても実際の行動に移すのは難しいことは古今東西の真理である。
以上の理由からプライバシーには踏み込まないことを前提とし、いつ踏み込まなければならないかを考える。
一つは治療にプライバシーに関する情報が病状や治療に必要な時である。当然患者にも前もって必要であることを告知し、その情報を聞き出す必要がある。また通院や退院後の計画を練る上でも必要な情報があり、それは正確に聞き出して、実行可能な計画を提案しなければならない。恐らく自分が医師の仕事に慣れてくると、そこらへんの感覚が鈍化して浮世離れしてしまう原因になるのではないかと今から危惧している。
もう一つは将来、生命に関わる危機がほぼ確実に起きることが予想できるときである。今回の症例で論点となった家族への告知は、妻及び子に感染の可能性があること、もし感染が成立していたらゆくゆくは模擬患者と同じような症状が現れることに対し、妻に知られることで離婚の可能性があると示唆する模擬患者との意見の対立であった。患者の言い分はもっともであったが、医療従事者の立場から感染拡大の可能性及び患者の服薬週間の獲得のために、家族へ告知すべきと判断し、患者本人の希望にそぐわない治療計画とした。今回のただしその場合も、あくまで告知する案を提案し推奨するまでで、提案しない場合の案も立案し、最終的な決断は患者にさせること、どちらにせよ決断した意志を尊重することを心がけた。