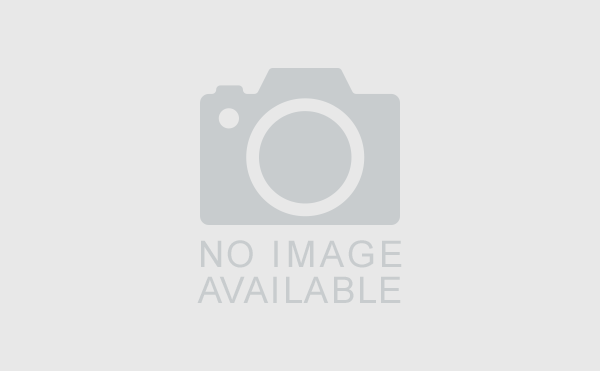役に立つか立たないかは、全て自分次第
神様のパズルという本を読みました。
天才少女と平凡な大学生が研究室の研究テーマに「無から宇宙を作り出す」ということを
本気で取りかかるところからスタートし、様々な物理的現象を用いながら
徐々にその方法を明らかにすると言ったような内容です。
なんであんな平凡な準教授とヒステリックな母親から、
時代を風靡するような天才が生まれてくるのかという微妙な疑問も生まれますが・・・
もやしもんという漫画があります。
大学生の主人公には、菌が見えるという特殊能力があり、
至って平凡な大学生活にその能力がちょっぴりエッセンスとしてストーリーが展開していきます。
でも基本的に菌が見える能力が活躍しないですが・・・
どちらの作品でも思ったのが、非常にその分野のことを勉強、研究しているということ。
特にもやしもんは、どこかの大学の教科書になるほど。
よく理系だからとか文系だからてな言葉を耳にしますが、ほんとはそんなの関係なくて、
自分に関係が薄い事でも何が役に立つかわからないことがよくあります。
逆に自分の仕事と全く関係ない事に詳しい方が強みになると思います。
この二つは特に顕著にそのことを示していて、例に挙げました。
ごく最近話題になった「探偵ガリレオ」も作者が工学部でリアルな科学的トリックと、
湯川学の変人ぶりが受けて人気が出ましたが、ここにも文学と科学の融合があります。
脚本家や映画監督にはこれに欠けてる人が多いようでしばしば幻滅します。
ドラマのガリレオも完全に湯川学のイメージのみが先行してましたし、
アルマゲドンも僕に言わせれば、コメディー映画の一つです。
結局文系の人も例えば文学者もある程度、世の中の理としての自然現象を知らなきゃ
視点の狭い作品になってしまうということがしばしばあるし、
法学でも、色々なことを知らなきゃ自分の仕事の範囲を狭めるだけですね。
経済学では数学的手法や論理的思考が必須であり、
いわゆる天才と呼ばれるような人達でなければ、発展していかないような状況にあると思います。
理系にも同じ事が言えて、文章の書き方を知らなければいくらすごい発見をしても
誰も論文を読んでくれないし、研究費はとってこれないし。
発表のスライドやポスターを如何に目立つようにするか、見やすい様にするかと考え出すと、
美的センスも必要になる。
そういう意味では、自分の役に立つか立たないかはその人の気の持ちようであって、
というか基本的には何かしらの役に立つのであって、
何かにつけて意味がないとか、役に立たないとか仰られる人をみると非常に残念になります。
最近おもしろいのでよく読んでいる日経BPの「デキルヤツノ条件」というコラムがありまして、
筆者の降旗学さんの考えが、くだけた文章と豊富な話題と鋭い切り口でこんな考え方もあるのかと、
むしろ驚きが多い様なコラムなのです。非常にお勧めです。(https://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20080305/148977/)
そんなコラムですが、かなり独特な事も手伝ってか、
「冗長、短く書け、結論がわからない、結論を先に言え、文章が砕けすぎている」などのコメントがちらほら見受けられますし、役に立たなかったと言う感想が半分以上というケースもたまにあります。
デキルヤツノ条件というのは、ひとそれぞれ多少なりとも違うのでしょうが、
少なくともこういうコメントを書かれると、
「自分はこれくらいの文章は長くて読めません、簡単に書いてくれないと理解できません。」
と吐露しているようにしか思えない。
文章も別のコラムの「長目飛耳」を書かれるほどの文章力の持ち主なんだから、
わざと意図して書いていることは間違いないはずです。
本人曰く、試し試されていると。
時間が惜しいのにわざわざコメントしちゃうような矛盾をはらんでいる人は絶対にデキル人ではないと思う。
自分でもわかってはいるんです。
ちょっと面白くない内容とメリハリのないしゃべり方をする人の発表でも、
そこには必ず自分にはない学ぶべき事があることを。
内容でなくても、あそこはこういう表現をすべきとか、スライドはこうした方が見やすいとか、
ああしたほうが、こうしたほうが・・・zzz
体は正直なのです。