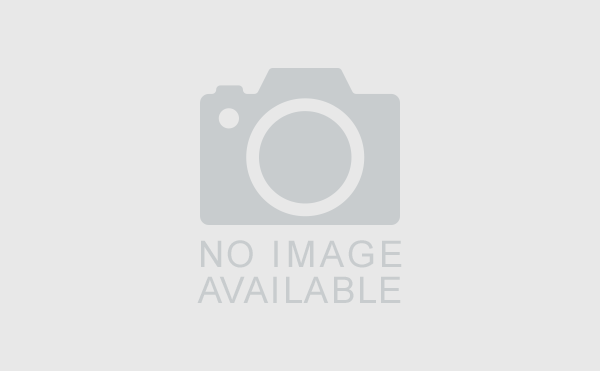mRNAワクチンについて
新型コロナワクチンのmRNAについて、そのメカニズムなどをつらつらと書いていきたいと思います。
- mRNAとは
- ワクチンとは
- 遺伝子組み換え技術とそのリスク
の三部作でお送りしたいと思います。
まずはmRNAの説明から始めます。
細胞内には生命の設計図となるデオキシリボ核酸(DNA)が存在します。DNAは塩基と呼ばれる4種類の物質、アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)があり、それぞれが数億個繋がって長い紐を形成しています。この塩基の並び方によってカエルになったり、人間になったり、人間の中でも様々な違いが出てきます。この並び方を遺伝子、遺伝情報と呼びます。例えるならDNAはパソコンの本体で、遺伝子はその中のファイルということになります。
でその遺伝子情報、ファイルから実際にどのように身体が出来上がるのでしょうか。そこには”転写””翻訳”という生命の神秘的なメカニズムが働いてきます。
まずは”翻訳”について説明します。A,T,G,Cの4種類の塩基の文字列はそれぞれ3つずつのグループに分けられます。例としては、ATC, ACA ,TGAなどで組み合わせは4の3乗で64通りあります。
その64通り全てに対応するアミノ酸が20種類存在しており、DNAの遺伝子情報に従ってアミノ酸がそれぞれ連なってタンパク質を組み立てていきます。そのタンパク質が身体を構成したり、酵素として生体反応を司ったりしていきます。
ここまでをまとめるとパソコン(DNA)に入っているファイル(遺伝子)から、組み立て(翻訳)することで生命が出来上がっています。
ここでいよいよmRNAの出番です。
細胞内で翻訳作業は絶え間なく行われ、様々なタンパクが作られています。一方で細胞内に入っているDNAは一つですので、翻訳に使うファイルをいちいちパソコン本体から読み込むと非常に効率が悪いわけです。
そこで使われているのがmRNAです。RNAもDNAとほぼ同様に4つの塩基(A, G, C, U(ウラシル))からなる長い紐です。電子機器に例えるならUSBメモリみたいなものでしょうか。パソコンからファイルをUSBメモリに取り出し、実際の組み立てが行われる現場まで持っていってタンパク質が組み立てられるというのが、生命活動の主な仕組みです。このUSBにファイルを取り出すという現象は、実際にはDNAをmRNAに”転写”すると呼ばれています。
また、一連の挙動は”セントラルドグマ”と呼ばれています。決してリ◯スがいるジ◯フロントの地下のことではないんですね。
mRNAの特徴もUSBと似ています。さまざまなタンパク質の電子ファイルとなりえるように、簡単に分解、組み立てができるようになっています。USBメモリも簡単にコピー、消去ができるようになっているのと同様です。
物質的には分解しやすいということは逆にいうとすぐ壊れてしまうということと同義です。mRNAワクチンを-75℃に保存しなければいけない理由はこんなところにあったわけです。