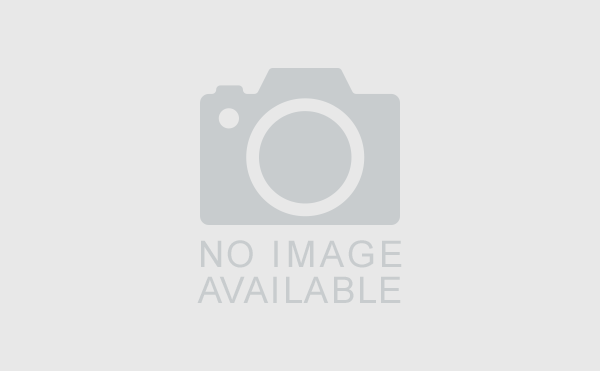アイと二人三脚で生きる (自我の話) Part2
前回の記事はこちら
前回の記事では、自分の体及び行動がその実多くをアイによって制御、支配されていることを考えました。
今回は、いよいよ自我について考えます。
突然ですが、あなたは寝食を忘れて何かに夢中になったことはないでしょうか?
空腹や眠気を我慢して、社会的、文化的な行為を優先したことはないでしょうか?
私はこの行動こそが自我であると考えます。
つまり、自身の興味や社会的責任を以って、アイを組み伏せ、遺伝子の乗り物から脱却した行為であると言えます。
これらの行為の原動力は強烈な興味や、誰かに対する奉仕の心などですが、単純化すると”好き”という感情です。
例えば3歳くらいの幼児は何かに強烈に興味を持つようになります。
よくあるパターンが男の子の自動車や電車好きですが、それが生命活動において何かのプラスに成るとは到底思えません。
しかしながら他に興味を持つということが、つまり自我の形成の始まりであるのです。
このような強烈な興味は集中を促し、空腹や眠気や情動を一時的に遠ざけることができます。
繰り返しになりますが、この瞬間はアイの支配下から自分の体を取り返しており、これこそが自我と呼べるものの正体ではないかと考え着きました。
また、この行為は比較的人間社会としても高い評価を受けやすいですし、自我の評価としてなんとなくでも自分たち自身も気づいているのではないかという推察ができます。
さらには、欲がない状態を”無我”の境地とも言いますから、自我が興味や嗜好であることを示唆しているものと思います。
この境地がどのようなものかは、比較的欲にまみれた私には理解しかねます。
恐らく、自分を無色にすることで、相対的に人の興味や欲が浮き彫りにされ、その人の悩みや思考を感じやすくなるのではないかと考えます。
興味の究極は自分自身に興味を持つことです。
自分はなんのために生まれて、生きるのか。
そのことに興味を持ち、たどり着いた結論が”我思う、故に我あり”だったのでしょう。
自分自身に興味を抱いた時点で、自我が生まれ、それこそが自分だという証明に気づいたフレーズだったのではないでしょうか。
ちなみに、自我によってアイをいじめていても、アイは黙々と仕事をしてくれます。
空腹を感じないようにアドレナリンやコルチゾールを分泌し、血糖値を上昇させ、血圧を上げ、栄養に乏しくても生命活動に支障がないよう調整してくれています。
一方でアイ自身には、空腹や情動を誘発する機能は付いていますが、何を好きになり、誰を好きになるかまではフォローできません。
それを決めているのがあなた自身、自我の機能であると考えられます。
ですから、”好き”を判断する臓器が自我の形成の最も関与しているとすれば、脳の中の扁桃体がその中心的な役割を示していることになるでしょう。
あなたの好きを集めたら、あなたになる。これが私が言いたかった自我の正体です。
このままだと自我とアイの喧嘩話で終わってしまうので、次回は二人三脚で考えてみたいと思います。