アイと二人三脚で生きる (自我の話)
・自己啓発的な話ではありません。あくまで現象から見た自我の機能と本質に言及します。
・専門家でもなければ、何かを参考にしているわけでもありません。妄想に近いです。
・自分を失っている奴が書いております。
・アイとはInstinct(本能)の頭文字です。
以上を念頭に入れてお読みください。
自分の脈を触覚で測るという違和感から、自己について考察してみました。
試しに読みながら、手首の脈を測ってみてください。触覚で測定しているのはまちがい無くあなただと思います。
動いている心臓もまちがい無くあなたのものだと思いますが、心臓を動かしているのは誰ですか?
もしそれがあなたであれば、わざわざ手首で脈など測らなくても分るはずで、つまりあなたでは知覚しえない、あなたではない誰かが動かしているということになります。
それは自分の中にいる、自分じゃない存在です。
その存在を仮にInstinctの頭文字からアイと名付けましょう。
アイは自分の体において多くの機能を統括しています。
心臓を動かすのはもちろん、内臓を動かし、血管を制御し、ホルモンを分泌し、体温を調節し、体液を分泌し・・・。
いわゆる不随意運動と呼ばれるすべての司令塔です。でもそれだけではありません。随意運動にも中心的な機能を担っています。
あなたが歩きたいと思った時に、アイはあなたの願望を翻訳し、各筋肉に指令を送ります。
あなたが、大腿四頭筋、大腿二頭筋、腓腹筋、広背筋、脊柱起立筋、腕なら三角筋、棘上筋、大胸筋などのそれぞれを全く意識しなくても、それらの筋肉が連携して動き、歩行を可能にしています。
時に、アイと折り合いが非常に良い人たちが居ます。彼らは錦織圭選手のようなトップアスリートになれるでしょう。
そうでなくても、反復練習を重ねることで折り合いが良くなっていきます。
これだけ聞くと、じゃあアイの正体は小脳かと思われるかもしれませんが、それも違います。大脳皮質もアイの管轄部署になっております。
次の文章を読んでみてください。 “私はあなたを愛しています”
何の変哲もない、日本語の文です。
ではこれは? “ялюблю тебя”
ロシア語でI love youという意味です。
私もgoogle先生を鵜呑みにしているので、正しいのかどうかすらわかりません。
私たちは無意識に日本語をみたらその意味までを瞬時に理解します。
そしてあなたは日本語を自分の意思で、意味のなさない文字列として認識することは不可能だと思います。
“私はあなたを愛しています”という文章を、発音もわからない文字列と自発的に認識できるでしょうか?
私自身、高校生の時に頑張って日本語を読めなくなれるよう努力してみましたが、どう頑張っても瞬時に認識してしまっておりました。
という具合に、人の真骨頂である言語能力にもアイは存在します。同様に聴覚や視覚にもアイは存在し、大脳皮質とてまだ自我ではありません。
では、歩きたいと思った存在が自我でしょうか?それも違います。
なぜ歩きたいと思ったか。
お腹が空いた、眠い、誰かとイチャイチャしたいなど、生物として必要な欲求を満たすために歩くことが多いと思いますが、ではお腹が空いたのは誰でしょうか。
これはアイの仕業です。
アイが自身の持つセンサーで血糖値の低下を感知し、それを我々がわかる形に翻訳したのが空腹です。同様に疲れを感じれば眠くなります。
つまりアイによって発信された命令を、さも自分が考えたかのように行動させ、またアイによって満腹や覚醒を引き起こされる。
この一連の動作に自我が入り込む隙間は少ないと思われます。
恐らく”利己的な遺伝子”論者は、ここまでの行動を鑑み、自我なんて実は存在しない、遺伝子の乗り物だという主張をしているのでしょう。実は真面目に読んだことないのですが。
ここまでの話だと、自分の体は大部分がアイによって統率され、乗っ取られ、いいように自我が使われていることになります。
でも、自我がアイを組み伏せる瞬間があると思います。 ネムイ続く。
“アイと二人三脚で生きる (自我の話)” に対して2件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。
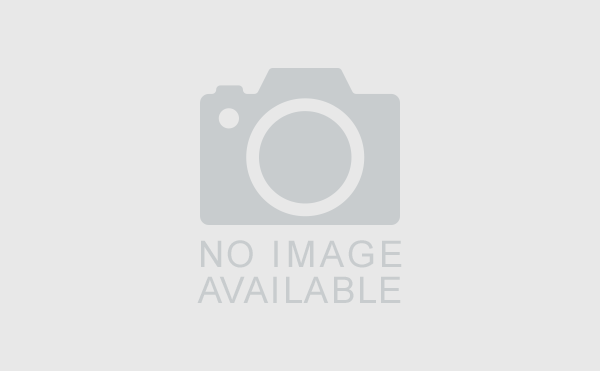
利己的な〜は自分も流し読みしました。
しばらく前に、何故カラスが賢いかを考えた事があって、カラスの集団行動が人間の1個体の行動に置き換えられるような気がして、色々調べ考えるうちに、遺伝子の乗り物って解釈が、腹に落ちたことがあります。
誰にも知覚出来ない、カラスの群れの総意と言うものがあるとして、それが人間1個体で言う自我に近いものかな、なんて。
Yuさん
コメントありがとうございます。群れを以て個体となす、いわゆる超個体の概念ですね。
それをあまり群れを成さないカラスにも適用できるというのはなかなか興味深い考察ですね。