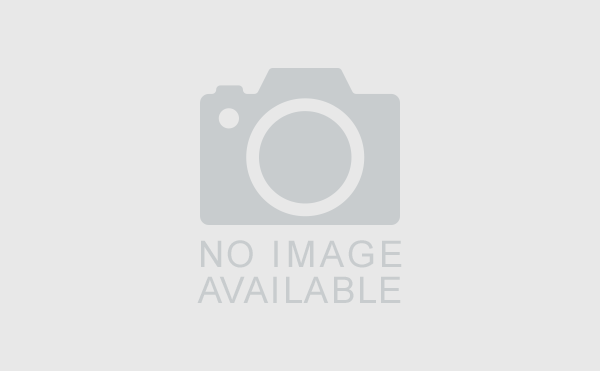界面活性剤とは
自分の理解の範疇で、界面活性剤をとことん丁寧に解説してみます。
界面活性剤=洗剤との認識ですが、
①界面とは何か
②界面を活性するとはどういうことか
③それがなぜ洗剤になるのか
という感じに分けて書きたいと思います。
①界面とは
界面とはある物質と物質の接している面のことを指します。
例えば、水と空気なら水面のこと、水と油ならそれぞれが接し合う面であり、
あらゆるものとものの間に界面が存在します。
ただし、人間社会に生きていて特にどうにかしたい場合が多いパターンは、
水と油の界面ということが多いので、特に何も言わずに”界面”とだけ書いてある場合は、
水と油の場合が多いです。
一方で、アルコールと水の界面はありません。
なぜならその二つの液体はともに極性があり、混ざり合うためです。
水と油が混ざらないのは、水には極性がある一方で、油には極性がないためです。
物質は自分の極性と似た極性とはよく混ざり、そうでない極性とは混じり合いにくいという特性があります。
例えば、水、アルコールはそうですし、油には食物油、シンナーとラッカー液、ロウなどがあります。
もし仮に、水と油が入っている容器をよく振って、なんとか混ぜ合わそうとします。
すると油が小さな雫となり、水の中に分散しますが、しばらくすると元に戻ってしまいます。
この油が小さな雫になった状態では、水と油の界面の表面積がただ接している時より多くなります。
この水と油の界面をものすごくミクロに見ると、水分子と油の分子が接している層が一面あります。
これらの接している分子は不安定で、なんとかお互いの分子に囲まれようとして、どんどん油の雫同士がくっつきあい、
やがてお互いの接する表面積が一番小さい状態まで集まります。
それが、水と油に分離した状態です。
接している分子の不安定さを”界面エネルギー”として数値化し、
水と油に分離しきった状態を”界面エネルギーが最も低い状態”と表します。
界面エネルギーそのものは実生活ではあまり実感しにくいのですが、
ラーメンの油が小さいときは丸くコロッとしているのに対し、
それをつなげて大きな状態にすると、輪郭が崩れてデロっとした状態になると思いますが、
前者を界面エネルギーが高い状態、後者を界面エネルギーが低い状態と認識していただけると、
イメージしやすいかと思います。
つまり界面とは、物質と物質の間の層であり、
放っておくと、界面エネルギーが一番低い状態に落ち着くということが言えます。