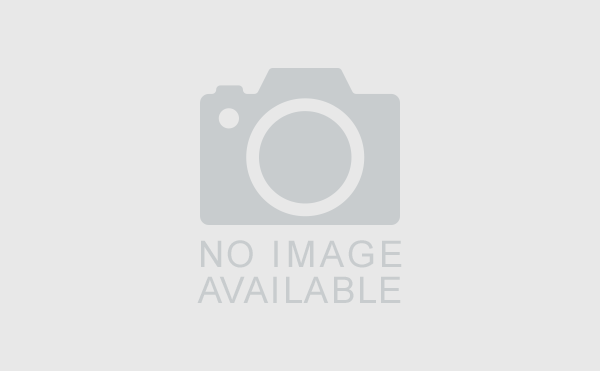頭痛の正体
脳神経外科として外来を始めてから数年が経ちました。
入院管理と違い、様々な方が外来にいらっしゃいます。
多くは脳梗塞や脳出血、慢性疾患に対する処方の継続の方が多いですが、
新規にいらっしゃる患者さんで多いのが頭痛。
そりゃ脳外ですからね。
頭痛には主にふたつに大別されます。
一次性頭痛と二次性頭痛です。
二次性頭痛は頭蓋内に原因がある頭痛を指します。脳出血などにより発症するものです。
一次性頭痛はそれ以外の画像検査では原因がわからないものを指します。
緊張性頭痛(こちらがいわゆる偏頭痛)や片頭痛(発症する人は少ない月に10日程度以上の慢性的な頭痛)、群発頭痛などをさします。
緊張性頭痛はたまに頭痛が起きる人や初めて頭痛が起きた人に多い頭痛です。
首の後ろやこめかみ、額にかけて、多くは右か左かどちらかでまれに両方出る方もいらっしゃいます。
手足の麻痺などを伴わず、痛みの程度に波があり、鎮痛薬がよく効くのが特徴です。
数年外来をしていて、緊張性頭痛は頭の筋肉のコリであることを実感しました。
というのも、緊張型頭痛の特徴の一つに、首の凝りや肩こりと併発し、多くは同じ側になります。
また、人によっては数日前に普段しない動きをした方も比較的多いです。
例えば草刈りや手紙を認める、ゴルフ、工場のラインに配属されたなどがこれまで実際にあった例です。
このように普段しない動きによって体の左右の使い方のバランスが崩れ、
片側に負担が集中し、肩こり、首凝り、頭痛とセットになることが多いように感じます。
人間の感覚とは不思議なもので、肩こりと首こりはちゃんとそこが痛いと認識でいるのに、
頭の筋肉、(頭板筋や側頭筋など)はなぜか頭痛として認識されます。
多くは筋肉の凝りなので、数日安静にすれば改善します。
また、職業による頭痛は就業によって引き起こされるため、弱目の筋弛緩剤を投与することで、
肩こりと共に改善する例もあります。
また、最近多いと感じるのは体調不良時に頭痛が酷くなったという例。
これも筋肉の凝りが関係しています。その原因がスマホ。
床にふせっていてやることがないので、ついついいじってしまいがちです。
ところがスマホの操作には両手が必要なものが多く、横向きに寝て、少し頭を持ち上げて操作する姿勢が多くなります。
さらに利き手も決まっているので、同じ姿勢を維持することが多いです。
その少し頭を持ち上げるという行動はかなり首の筋肉の負担になります。
気づいたら筋肉が凝って頭痛を引き起こしがちです。
また、体調不良時に辛くて眉間に皺を寄せ続けても前頭部の筋肉の凝りを誘発し、頭痛になりがちです。
とはいえ、脳神経外科も診察時に病状などを聞いてある程度は判断しますが、
最終的に画像検査(CTやMRI)を撮影するまで実際の診断はつけにくいです。
私の師匠もとにかく脳外は画像をとらなきゃ何にもできないと言っていたので、私もそのスタンスを踏襲しています。
また、怖い頭痛が潜んでいるのも事実なので、少しでも不安に感じたら受診することをお勧めします。
ただ、数日前からある頭痛に対して、夜中(特に休日の夜中)に救急車を呼ぶのは控えてください。
日中の医師の体力と人足が充実している時間に医療機関を受診することをお勧めします。