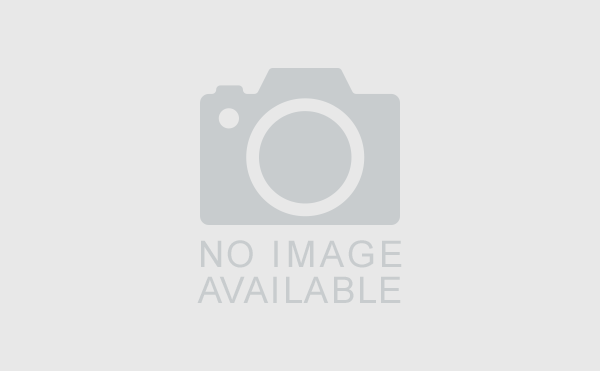痩せるという化学反応 〜エネルギー代謝 糖〜1
痩せるということは体の中の脂肪が減るということです。
昨今のダイエットはその現象をなぜかカロリーで管理しているという点に問題があることを指摘しました。
一方で体の中の脂肪を減らすという理屈を理解するためには、体の中で糖やタンパク質、脂質がどのような化学反応を経てエネルギーに変換されるかを理解する必要があります。
みなさんの中には漠然と、運動などを行ってカロリーを消費すると燃焼によって脂肪が”消失”するというイメージをお持ちの方もいると思います。これは間違っています。
脂肪1kg分のエネルギーを消費したら、脂肪がなんらかの化学反応を起こし、脂肪でないものに変換されて、体のどこかしらからしっかり排出されています。
この脂肪や糖などの物質の出入りを、化学工学の用語を用いると”物質収支”と言います。
この物質収支を理解することで、これまでカロリー管理のダイエットから、実際の食べたものと出ていくものの具体的なイメージを持ってダイエットを管理できるように、知識がアップデートされます。
そのためにはまず、体内での複雑なエネルギー代謝の反応と向き合ってみましょう。
それぞれの物質は複雑ですが、イメージを用いながらなるべくわかりやすく説明していきたいと思います。
この世の生きとし生けるものの全てのエネルギーの基本は糖です。正確にはグルコースです。微生物も植物も動物もグルコースを化学反応によりエネルギーに変換し生命活動をおこなっております。
糖には様々な種類があります。単糖と呼ばれるグルコース、フルクトース(果糖)、ガラクトースがあり、それら二つが化学的に組み合わさった二糖類、グルコースが多数化学的に組み合わさったアミロース(澱粉)やアミロペクチン(お餅の粘り気)などがあります。
これらは全て体内でグルコースに変換されて吸収され、エネルギー代謝に活用されます。
エネルギーを取り出す化学反応の基本は”酸化”です。現在の地球は酸素に満ち溢れているため、物質は放っておくと容易に酸化されます。酸化の身近な現象として”燃焼”が挙げられます。これはおもに植物のセルロースが”酸化”しCO2となったときに生成される、熱エネルギーと光エネルギーを観察していることになります。ですので、体内でエネルギーを消費する際に”燃焼”といった例え方をするのです。
実は何かの物質が酸化されると同じ量だけ何かの物質が”還元”されます。この”還元”は酸化の全く逆の反応と言っていいのですが、全ての物質が酸化の方向に向かいやすい現在の環境において、還元された物質はその分だけエネルギーを蓄えていると言えます。例えば、酸化されきったCO2を光エネルギーを使ってブドウ糖に”還元”するのが植物の光合成です。言い換えるとブドウ糖には光エネルギーの分だけ”エネルギー”が貯蓄している状態にあります。
植物のセルロースも”還元”された状態にあるために、酸素と結びつくことによって熱エネルギーと光エネルギーを生成することができるわけです。
体内でも同じことが起きていて、ブドウ糖を”酸化”し、体内にある物質を”還元”することによって、ブドウ糖のエネルギーを体内に貯蓄しています。これら一連の流れが体内にエネルギーを取り込んでいるメカニズムとなります。
今回は概念的なお話にとどまりましたが、次回はそのメカニズムを詳しく説明していきます。