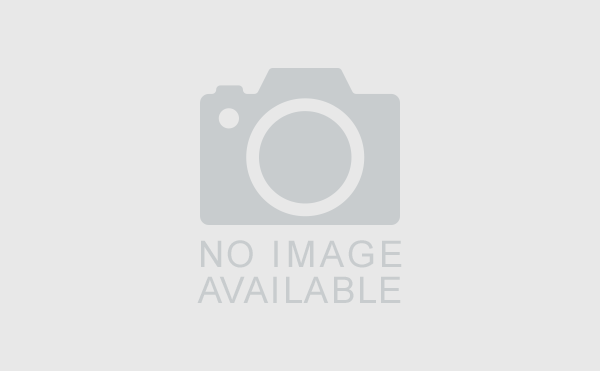痩せるという化学反応 〜エネルギー代謝 脂肪〜2
それでは脂肪の代謝反応を見ていきます。脂肪の代謝はβ酸化と呼ばれています。
脂肪もタンパク質と同様に体内の糖が不足し、飢餓状態になった時に代謝されエネルギーに変換されます。とはいえ、生物全般に言えることですが、起きている時ずっと食事を取る必要がないのは、直後に糖をエネルギー源として用い、体内の糖が減ってきたら脂肪をエネルギーに変えているおかげですので、ある程度空腹になれば日常的に脂肪の代謝が行われています。
脂肪がグリセリンと3つの脂肪酸からなっていることを前回説明しました。
脂肪が代謝される時は再度脂肪酸とグリセリンに分解され、その脂肪酸が使われます。
脂肪酸は炭素が長く連なった化合物ですが、その炭素を2個ずつ取り出し、アセチルCoAという物質が合成されます。
このアセチルCoAという物質は、本来であれば糖から分解されてクエン酸回路に補充される物質です。この物質を脂肪から直接作れるため、糖が体内で枯渇した時でもクエン酸回路を回し、ATPを合成し、必要な生命活動を維持できるというわけです。
タンパク質とは異なり、脂肪にはあまり生理的な機能は少ないですから、純粋な貯蔵エネルギーとして体内で用いられます。
グルコース1分子からは2分子のアセチルCoAが作られますが、脂肪酸1分子からは8~9分子のアセチルCoAが生成されます。分子量がグルコースが180g/mol、脂肪酸が300g/molくらいでです。単純計算でも脂肪酸からは糖と同じ重さで2〜3倍のエネルギーが取り出せる計算になります。また、先に述べたように水に溶けずに体内に貯蔵できるため、エネルギー源としては理想的な物質であることが数字からも読み取れます。
つまり100gの糖分を我慢しても、30gの脂肪しか燃えないんですね。糖分の誘惑を断ち切り、この理想的な物質を相手にして、痩せなければならないのでダイエットは困難を極めるわけです。
次回は脂肪代謝と呼吸の深い関係について説明したいと思います。