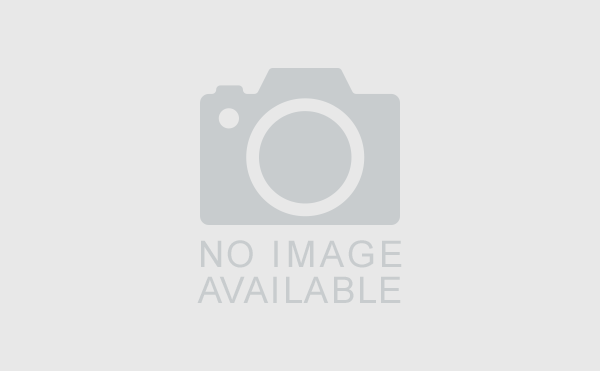必需品と贅沢品
昨今の少子化に関して、現在二児の親として子育てしている身として感じることを赤裸々に書こうと思います。
おそらく分岐点は高度経済成長期だと思います。
それまでの社会では一次産業としての農業に従事している人が大半を占めていて、インフラを維持する人、浮いた銭で行く多少のサービス業の社会的構造であったと予想します。
その頃は人数=力であり、子供が増えることは歓迎されることでした。(児童労働を認めているわけではありません)
農業に関しても、家に子供がいても特に仕事の邪魔になるわけでもないですし、その頃は医療も今より発達しておりませんから、産めよ増やせよという社会的風潮であったのだと思います。
そして時は高度経済成長期。産めよ増やせよで生まれ、地元に働き口がなくなった人達が外貨を稼ぐ国策と相まって、大量に工業分野やサービス業に従事し始めます。
同時に農業も効率化や農地転換などの政策もあり、次第に1次産業に従事する人の割合も少なくなってきます。
しかしまだこの頃はいわゆる働き手としての夫と専業主婦という構図ができており、子供がいても、支出には多少の影響があっても、家庭への収入の影響は少なかったと思います。
やがて社会が成熟し、ほとんどの人がサラリーマンとして働くようになりました。また女性の社会進出気運も相まって、いわゆる共働きが増えてきます。
そうなると子供の存在は家庭の支出だけでなく、収入に直結します。もちろん社会制度的にそうならないような制度が整備されている会社もあります。
それでも産休、育休中は収入が低下しますし、保育園料はかかってきます。
そのような支援がない職業や自営業、アルバイトなどでは激減してしまう例もあるでしょう。
一方で子供側も昔のように家計の足しになるかと言えばそうはなりません。
それぞれの段階まで教育を受けた後は独立し、独自に家計を営んでいくことになるでしょう。
そうなるともうね、親世代として生きていく上では邪魔な存在になってしまうのですよ。
もちろん、子供がいることによるかけがえのない時間は貴重なものです。
しかしながらその貴重な時間を捻出すること自体が所謂贅沢な時間になってしまっているのが現状です。
もちろん世代を紡がないことには国も成り立ちませんし、生物としての種の存続という面もありますが、
子供のいる世帯の自己犠牲に成り立っていると言ってもいいと思います。
この流れの中にあって、さらに昨今の増税や社会保障費の増大、実質賃金の長期低下などが上乗せされているのです。
この社会的構図の変遷に立ち返ると、出生率を改善するには少なくとも高度経済成長期の専業主婦が成り立ち、クレヨンしんちゃんのような家庭が一般的になる時代まで、1馬力の収入を戻さなければならないでしょう。
もちろん企業だけの責任ではありません。
昔痛みを伴う改革とおっしゃってた方がいらっしゃいましたが、是非これから死に行く世代には痛みを伴って、これからの世代へ資源が回るように意識改革や構造改革をしていただきたいものです。