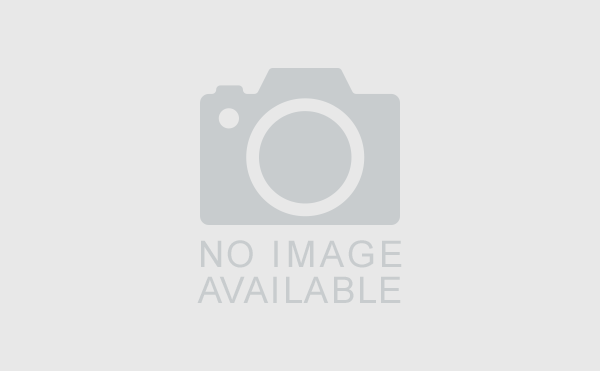114回 医師国家試験 Eブロック
1 人生の最終段階〈エンド・オブ・ライフ〉における医療およびケアの意思決定について適切なのはどれか。
a 患者本人の意思が確認できない場合は家族の意向に従う。
b 患者本人の意思が確認できる場合は患者の意向を尊重する。
c 患者が認知症の場合は患者本人の意思が確認できないと判断する。
d 患者本人の意思決定能力の判断には精神科医の診察が必要となる。
e 患者の配偶者と実子の意見が対立する場合は配偶者の意見を優先する。
2 局所麻酔下で患者に外科的処置を行う際の正しい方法はどれか。
a 麻酔薬の注射には18G針を使用する。
b 滅菌シーツの穴より狭い範囲で消毒する。
c ポビドンヨードを塗布後、直ちに処置を行う。
d 麻酔薬の注射後、疼痛の有無を確認してから処置を行う。
e 注射針を刺入し血液逆流があることを確認してから麻酔薬を注入する。
3 地域保健について正しいのはどれか。
a 予防接種の実施主体は教育委員会である。
b 地方衛生研究所は主に対人サービスを行う。
c 地域包括支援センターの設置主体は都道府県である。
d 医療安全支援センターの業務は医療法に規定されている。
e 地域保健センターには必ず医師を置かなければならない。
4 他の医療機関で異常を認めないと説明された後も、不安が続いている患者が来院した。
対応する医師の医療面接における言葉として適切でないのはどれか。
a 「あなたの気持ちを聞かせてください」
b 「どのような病気を心配されていますか」
c 「異常を認めないと言われても不安があるのですね」
d 「心配し過ぎるあなたの性格に問題があるように思います」
e 「不安をお持ちでしょうが、それでもよく頑張っていますね」
5 意識障害のある患者の眼の診察で、最も緊急性が高い所見はどれか。
a 眼脂
b 翼状片
c 眼球結膜の出血
d 眼瞼結膜の充血
e 瞳孔径の左右差
6 喫煙に関して正しいのはどれか。
a 喫煙の依存性はタールが原因である。
b PM2.5はタバコの煙に含まれている。
c 屋内の分煙により受動喫煙を防止できる。
d 喫煙による発癌はニコチンが主因である。
e 禁煙すれば肺癌死亡率は非喫煙者と同じになる。
7 成人の頸部・前胸部(A)、上腕部・前腕部(B)を別に示す。
成人における末梢挿入中心静脈カテーテル〈PICC〉の適切な刺入部位はどれか。
a ①
b ②
c ③
d ④
e ⑤
8 輸血後GVHDで正しいのはどれか。
a 輸血後6時間以内に発症する。
b 新鮮血と比較して保存血で起こりやすい。
c 輸血製剤の放射線照射が予防に有効である。
d 初回と比較して複数回の輸血後に起こりやすい。
e 血縁者と比較して非血縁者からの供血で起こりやすい。
9 月経周期におけるホルモン変動と関連がないのはどれか。
a 体重
b 中間期出血
c 乳房緊満感
d 透明な頸管粘液
e 黄色泡沫状腟分泌
10 直径10cmの子宮筋層内筋腫が原因となって生じ得るのはどれか。
a 片頭痛
b 無排卵
c 過多月経
d 希発月経
e 月経前症候群
11 触診による腹膜刺激徴候の確認で誤っているのはどれか。
a 患者の表情に注意する。
b 自発痛がない部位から始める。
c 打診で痛みを訴える部位には慎重に行う。
d 腹膜刺激が顕著な部位の触診は必要最小限にする。
e 反跳痛〈rebound tenderness〉は手掌全体で押さえて確認する。
12 抗菌薬の使用で正しいのはどれか。
a 解熱後はすぐに抗菌薬を中止する。
b 発熱のある患者には抗菌薬を投与する。
c 細菌検査の検体を採取後に抗菌薬を投与する。
d 感受性検査の結果によらず広域抗菌薬を継続する。
e 解熱薬を併用することで抗菌薬の効果判定が容易になる。
13 うつ病でみられるのはどれか。
a 誇大妄想
b 罪業妄想
c 追跡妄想
d 被毒妄想
e 物盗られ妄想
14 医師が学術会議で発表する際、職業倫理に反する行動はどれか。
a 発表内容に関する利益相反を公表する。
b 患者の個人情報を特定できないようにする。
c データを自分の仮説に合うように改ざんする。
d 自分が経験した複数の症例をまとめた内容を発表する。
e 医療機器メーカーから研究助成を受けた研究結果を発表する。
15 多職種でのチーム医療を妨げる要因はどれか。
a 職種独自の略語を使用する。
b 患者の家族の希望を傾聴する。
c 他職種からの意見を尊重する。
d 各職種の専門性が確立している。
e 他職種の役割や機能を理解する。
16 HbA1cについて正しいのはどれか。
a 貧血の影響を受ける。
b グルコース以外の糖類も影響する。
c 過去1~2週間の血糖状況を反映する。
d 赤血球内の酵素反応により形成される。
e 我が国のメタボリックシンドロームの診断基準に含まれている。
17 ランダム化比較試験〈RCT〉について正しいのはどれか。
a 二重盲検は必須である。
b プラセボは現在では使用が禁止されている。
c ランダム割付は症例数を少なくするために行われる。
d 症例数の設定のためには治療効果の推定が必要である。
e Intention to treat〈ITT〉による解析は実際に行った治療に基づいて行われる。
18 ノーベル生理学・医学賞を受賞した日本人研究者とその研究者が貢献した研究内容の組合せで誤っているのはどれか。
a 大隅良典 ——— オートファジーの仕組みの解明
b 大村智 ——— マラリアに対する新たな治療法の発見
c 利根川進 ——— 抗体の多様性に関する遺伝的原理の発見
d 本庶佑 ——— 免疫チェックポイント分子の発見
e 山中伸弥 ——— 成熟した細胞のリプログラミングによる多能性の獲得
19 触診上、皮膚表面が平滑なのはどれか。
a 脂肪腫
b Bowen病
c 尋常性疣贅
d 脂漏性角化症
e ケラトアカントーマ
20 等張液でないのはどれか。
a 生理食塩液
b 5%ブドウ糖液
c 酢酸リンゲル液
d 乳酸リンゲル液
e 25%アルブミン液
21 健常成人の血中濃度で食事により値が低下するのはどれか。
a GH
b インスリン
c グルコース
d トリグリセリド
e 遊離サイロキシン〈FT4〉
22 糖尿病腎症による腎機能予後を観察研究で調査することにした。
アウトカムとして臨床的に最も重要なのはどれか。
a HbA1c
b 腎不全
c 蛋白尿
d 下腿浮腫
e 病理所見
23 脳梗塞で入院した患者に対し、言語聴覚士が評価を行うのはどれか。
a 見当識
b 嚥下機能
c 巧緻運動
d 四肢筋力
e 心理状態
24 70歳台の女性が初めての失神を主訴に救急外来を受診した。
血糖測定とともにまず行うべき検査はどれか。
a 脳波検査
b 頸椎MRI
c 心電図検査
d 頸動脈エコー検査
e 胸部エックス線撮影
25 麻疹ウイルスと同様の感染経路別予防策を要するのはどれか。
a A群レンサ球菌
b ムンプスウイルス
c 水痘帯状疱疹ウイルス
d 多剤耐性緑膿菌〈MDRP〉
e メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉
26 42歳の女性。発熱および悪寒戦慄が出現し、ぐったりしていたため家人に連れられて来院した。昨日の夕方に悪寒戦慄を伴う発熱が出現したため受診した。咽頭痛、咳、痰および鼻汁はない。悪心、嘔吐、腹痛および下痢はなく、頻尿や排尿時痛もない。周囲に同様の症状の人はいない。小児期からアトピー性皮膚炎があり、数日前から皮膚の状態が悪化し全身に掻痒感があり掻破しているという。意識レベルはJCS I-2。体温39.2℃。脈拍112/分、整。血圧86/58mmHg。呼吸数28/分。心音と呼吸音とに異常を認めない。口腔内と咽頭とに異常を認めない。両側背部の叩打痛はない。顔面、体幹部、両側上肢および両側膝の背面部で紅斑、色素沈着、鱗屑および落屑を認める。また、同部に多数の掻破痕および一部痂皮を認める。
最も適切な検査はどれか。
a 尿培養
b 血液培養
c 喀痰Gram染色
d 麻疹抗体価測定
e インフルエンザ迅速検査
27 日齢0の新生児。在胎39週5日、経腟分娩で出生した。啼泣が弱く、保温および口腔内の羊水の吸引と皮膚への刺激を行った。出生後30秒の時点で自発呼吸を認めず、心拍数110/分であった。
まず行うべき対応はどれか。
a 気管挿管
b 胸骨圧迫
c 生理食塩液の静脈内投与
d アドレナリンの静脈内投与
e バッグバルブマスクによる人工呼吸
28 38歳の初妊婦(1妊0産)。妊娠34週に激しい腹痛と性器出血のため救急車で搬入された。これまでの妊娠経過は順調であったが、妊娠33週の妊婦健康診査で両下腿の浮腫と尿蛋白、軽度の血圧上昇を指摘されていた。喫煙は、妊娠前は20本/日であったが、妊娠後は5本/日に減らしている。体温36.9℃。心拍数72/分、整。血圧170/90mmHg。腹痛のため表情は苦悶様で、腹部は膨隆しており板状に硬く、圧痛を認める。腟鏡診で少量の性器出血を認め、内診で子宮口は閉鎖している。尿蛋白2+。超音波検査で子宮底部に存在する胎盤の著明な肥厚を認める。胎児心拍数陣痛図で基線細変動の減少と遅発一過性徐脈を認める。
最も考えられるのはどれか。
a 切迫早産
b 切迫流産
c 前置胎盤
d 絨毛膜羊膜炎
e 常位胎盤早期剥離
29 28歳の男性。ふらつきを主訴に家族に伴われて来院した。高校在学中に不登校となり、そのまま自宅2階の自室に引きこもるようになった。高校は退学となり、仕事には就かず1日中カーテンを閉め切ってオンラインゲームに熱中していた。食事は母親が自室の前に提供していたが偏食が激しい。3か月前から夜にコンビニエンスストアに出かける際に暗いところで歩行が左右にふらついていることに家族が気付いていた。立ちくらみはなく、日中はトイレに行くときに見かけるのみだが、ふらつきはみられないという。喫煙歴と飲酒歴はない。眼瞼結膜に貧血はなく、心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。神経診察では眼球運動は正常で眼振を認めない。指鼻試験および膝踵試験に異常を認めない。不随意運動はみられない。腱反射は全般に低下しており起立閉眼で体幹の動揺が増強する。
ビタミンB12とともにこの患者の症状の原因と考えられる不足栄養素はどれか。
a 鉄
b 銅
c 葉酸
d ビタミンD
e マグネシウム
30 72歳の女性。左膝関節痛を主訴に来院した。2年前に歩行時の左膝関節痛を自覚し徐々に悪化している。最近歩行が困難になったため受診した。左膝関節の外傷歴はない。身長155cm、体重64kg。体温36.3℃。脈拍64/分、整。左膝関節に膝蓋跳動と内反変形とを認めるが発赤と熱感はない。左膝関節エックス線写真を別に示す。
今後の対応の説明で誤っているのはどれか。
a 「大腿部の筋力を強くしましょう」
b 「杖の使用は避けてください」
c 「正座は避けてください」
d 「体重を減らしましょう」
e 「手術療法は有効です」
31 48歳の男性。意識障害と右片麻痺のため救急車で搬入された。自発開眼はなく、呼びかけでも開眼しないが、痛み刺激で開眼する。痛み刺激でうなり声をあげるが、意味のある発語はみられない。痛み刺激で右上下肢は全く動きがみられないが、左上下肢は払いのける動作を示す。
Glasgow Coma Scaleによる評価の合計点として正しいのはどれか。
a 3点
b 6点
c 9点
d 12点
e 15点
32 43歳の男性。健康診断のため来院した。喫煙歴は20本/日を13年間。朝、目覚めて5〜30分以内に最初の喫煙をする。最近、喫煙本数を減らしたところ、毎日イライラが高じているという。身長170cm、体重80kg。血圧150/90mmHg。
禁煙の短時間支援として誤っているのはどれか。
a 喫煙状況を把握する。
b 禁煙外来を紹介する。
c 喫煙の危険性を説明する。
d 禁煙の重要性を説明する。
e 喫煙量を戻すように指導する。
33 23歳の女性。発熱と頭痛を主訴に来院した。昨日から38℃の発熱、頭痛および頻回の嘔吐があり受診した。鼻汁、咽頭痛、咳嗽および排尿時痛はいずれも認めない。意識は清明。身長155cm、体重48kg。体温39.6℃。脈拍104/分、整。血圧108/50mmHg。呼吸数22/分。SpO2 99%(room air)。頸部リンパ節腫脹を認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。背部に叩打痛を認めない。項部硬直とKernig徴候を認めないがjolt accentuationを認める。尿所見:蛋白(−)、糖(−)、ケトン体(−)、潜血(−)、白血球(−)。血液所見:赤血球440万、Hb 13.0g/dL、Ht 44%、白血球3,600(桿状核好中球9%、分葉核好中球55%、好酸球3%、好塩基球2%、単球4%、リンパ球27%)、血小板14万。血液生化学所見:尿素窒素26mg/dL、クレアチニン1.1mg/dL、Na 135mEq/L、K 4.1mEq/L、Cl 93mEq/L。CRP 0.3mg/dL。血液培養の検体を採取し、抗菌薬治療を開始した。
次に行うべきなのはどれか。
a 尿培養
b 便培養
c 咽頭培養
d 喀痰培養
e 腰椎穿刺
34 72歳の女性。高血圧症で通院中の内科外来にて、夫への対応に困っていると相談があった。夫は2年前に職場を退職した後から飲酒をするようになり、最近はほとんど外出もせず、朝から家で飲酒することが増えた。飲酒をすると大声を出して暴れることがある。飲酒をやめるように話しても言うことを聞かず、病院受診を勧めると「病人扱いをするのか」と怒り出すため、とても困っているという。
この相談を受けた医師の対応として最も適切なのはどれか。
a 直ちに警察に通報する。
b 精神科受診のための紹介状を作成する。
c 夫に直接連絡し、禁酒するよう説得する。
d 地域包括支援センターに相談するよう説明する。
e 地域の在宅医に連絡し、夫に対する訪問診療を依頼する。
35 A 42-year-old woman came to your clinic, anxious about a mass in her left breast. On physical examination, the mass was hard and fixed neither to skin nor to muscle. No axillary lymph nodes were palpated on either side. Mammography showed a 2.5-cm lesion with spiculae. Histo-pathological findings from the biopsy showed an invasive ductal carcinoma. No metastases were detected on chest/abdominal CT or on bone scintigraphy.
What is the most appropriate plan at present?
a Breast surgery
b Estrogen administration
c NSAID administration
d Observation
e Whole body irradiation
36 71歳の男性。血痰を主訴に来院した。2か月前から微熱があり、2週前から断続的に血痰の排出が続いている。かかりつけ医で糖尿病の内服加療中であるが、コントロールは良くないと言われているという。呼吸音は両側胸部にcoarse cracklesを聴取する。胸部エックス線写真(A)及び胸部造影CT(B、C)を別に示す。
次に行うべき検査はどれか。
a FDG-PET
b スパイロメトリ
c 喀痰抗酸菌検査
d 尿中肺炎球菌抗原検査
e 血漿EGFR遣伝子検査
37 48歳の女性。排便後の出血を主訴に来院した。日頃から硬便であり、時々、排便後に肛門を拭いた紙に鮮血が付着していた。昨日、付着する血液量が多かったため受診した。
直腸・肛門指診の手順で誤っているのはどれか。
a 仰臥位で診察する。
b 手袋を着用する。
c 肛門周囲を視診する。
d 示指に潤滑剤を塗り肛門内に挿入する。
e 直腸内腔や肛門管内の触診をする。
38 28歳の男性。一過性の意識消失のため救急車で搬入された。会社で椅子に座っていたところ、突然目の前が真っ暗になり意識を失った。目撃者によるとけいれんはなく、1分ほどで意識が元に戻ったという。心配した会社の同僚が救急車を要請した。家族歴は父親が54歳で突然死している。意識は清明。心拍数64/分、整。血圧120/70mmHg。呼吸数16/分。心音と呼吸音とに異常を認めない。神経診察で異常を認めない。心電図を別に示す。
意識消失の原因として考えられるのはどれか。
a 状況失神
b てんかん
c 心室性不整脈
d 上室性不整脈
e 迷走神経反射
39 71歳の男性。6か月前からの排尿困難と夜間頻尿を主訴に来院した。既往歴および家族歴に特記すべきことはない。身長162cm、体重60kg。体温36.4℃。脈拍72/分、整。血圧154/82mmHg。呼吸数14/分。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。直腸指診で横径40mm程度の前立腺を触知するが硬結を認めない。尿所見:蛋白(−)、糖(−)、沈流に赤血球と白血球とを認めない。血清PSA 2.5ng/mL(基準4.0以下)。国際前立腺症状スコア28点(軽症0〜7点、中等症8〜19点、重症20〜35点)。腹部超音波検査で推定前立腺体積60mL。尿流測定で排尿量120mL、最大尿流率2.5mL/秒、残尿量240mL。
治療薬として適切でないのはどれか
a α1遮断薬
b 抗コリン薬
c 抗男性ホルモン薬
d 5α還元酵素阻害薬
e PDE 5〈phosphodiesterase 5〉阻害薬
40 65歳の男性。吐血のため救急車で搬入された。10年前からアルコール性肝障害を指摘されていたが通院していなかった。本日、夕食後に吐血をしたため、家族が救急車を要請した。意識レベルはJCS II-10。身長168cm、体重74kg。体温36.8℃。心拍数112/分、整。血圧88/68mmHg。呼吸数22/分。SpO2 95%(鼻カニューラ3L/分酸素投与下)。皮膚は湿潤している。眼瞼結膜は貧血様で、眼球結膜に軽度の黄染を認める。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部はやや膨隆し波動を認める。四肢に冷汗を認める。
まず行うべきなのはどれか。
a 輸液
b 胃管留置
c 腹腔穿刺
d AED装着
e 尿道カテーテル留置
41 次の文を読み、以下の問いに答えよ。
72歳の男性。下腹部痛を主訴に来院した。
現病歴:10年前から高血圧症で通院中であり、降圧薬による内服療法を受けている。1か月前から動悸を伴う心房細動が出現し、抗不整脈薬と抗凝固薬の処方も受けていた。昨日昼から尿が出ず、下腹部が張ってきていたが様子をみていた。今朝、下腹部の痛みで目覚め、症状が増悪するため受診した。
既往歴:特記すべきことはない。
生活歴:喫煙歴は20本/日を40年間。飲酒は日本酒1〜2合/日。
家族歴:父親が68歳時に胃癌で死亡。
現 症:意識は清明。身長165cm、体重61kg。体温36.9℃。脈拍52/分、不整。血圧142/94mmHg。呼吸数18/分。SpO2 96%(room air)。頸静脈の怒張を認めない。心尖部を最強点とするII/VIの収縮期雑音を認める。呼吸音に異常を認めない。腹部は下腹部が膨隆し、圧痛を認める。下腿浮腫は認めない。腹部超音波検査で膀胱容積は拡大しており、尿道カテーテルを一時的に留置することとした。
カテーテル留置で正しいのはどれか。
a 挿入時は患者を側臥位にする。
b 陰茎に潤滑剤を塗布した後に消毒を行う。
c 陰茎は垂直方向に軽く引き上げるように保持する。
d 蓄尿バックは膀胱と同じ高さの位置でベッド柵に固定する。
e 挿入途中で抵抗が強い場合、その位置でバルーンを膨らませる。
42 外来での処置中、検査室から「パニック値が出ているので、検査結果を至急報告します」との連絡があった。
検査所見:尿所見:蛋白2+、糖(−)、潜血2+、沈査は赤血球30〜50/HPF、白血球1〜4/HPF、細菌(−)。血液所見:赤血球450万、Hb 13.2g/dL、Ht 42%、白血球8,200、血小板24万、PT-INR 1.9(基準0.9〜1.1)。血液生化学所見:総蛋白6.8g/dL、AST 44U/L、ALT 20U/L、尿素窒素68mg/dL、クレアチニン3.8mg/dL、血糖136mg/dL、Na 134mEq/L、K 7.2mEq/L、Cl 106mEq/L、Ca 8.4mg/dL。CRP 1.2mg/dL。
直ちに行うべき対応はどれか。
a 腹部CT
b 心電図検査
c 膀胱鏡検査
d 動脈血ガス分析
e 部位を変えての静脈採血
43 次の文を読み、以下の問いに答えよ。
49歳の男性。動悸と息苦しさを主訴に来院した。
現病歴:今朝、朝食時に強い動悸を自覚し、息苦しさを伴っていた。自分で脈を触れたところ脈のリズムは不整で、脈拍数は112〜124/分であったという。動悸や息苦しさは2時間程度持続したが症状は徐々に改善し、来院時には消失していた。
既往歴:高尿酸血症を指摘され食事療法を行っている。
生活歴:喫煙歴は40本/日を24年間。飲酒歴はビール3L/日を29年間。
家族歴:心疾患の家族歴はない。
現 症:意識は清明。身長167cm、体重79kg。体温36.2℃。脈拍80/分、整。血圧152/94mmHg。呼吸数18/分。SpO2 97%(room air)。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。
検査所見:血液所見:赤血球463万、Hb 14.5g/dL、白血球7,600、血小板20万。血液生化学所見:AST 35U/L、ALT 38U/L、γ-GT 47U/L(基準8〜50)、尿素窒素18mg/dL、クレアチニン1.1mg/dL、尿酸8.1mg/dL、Na 138mEq/L、K 4.9mEq/L、Cl 101mEq/L。胸部エックス線写真で心胸郭比57%。心電図は、心拍数76/分の洞調律で、有意なST-T変化を認めない。心エコー検査で左室の拡張末期径は58mmと拡大し、駆出率は45%と低下している。
動悸の原因の鑑別に最も有用な情報はどれか。
a 家族歴
b 喫煙歴
c 高尿酸血症
d 動悸時の脈のリズム
e 来院時の心電図所見
44 飲酒習慣に関する説明として誤っているのはどれか。
a 「多量の飲酒は血圧を上昇させます」
b 「多量の飲酒は心不全を起こしやすくします」
c 「多量の飲酒は不整脈を起こしやすくします」
d 「禁酒により心機能障害の回復が期待できます」
e 「心臓に悪影響を与えないためにはお酒の種類を変更すればよいです」
45 次の文を読み、以下の問いに答えよ。
20歳の男性。医学部在籍中の2年次学生である。1週間の病院実習に初めての参加を予定しており、10か月前(1年次)に受けた抗体検査の結果を持って病院実習担当の医師に相談に来た。
既往歴:感染症の既往はないという。予防接種で発熱などの副反応が出たことはない。
生活歴:喫煙歴と飲酒歴はない。
家族歴:特記すべきことはない。
検査所見:10か月前の抗体検査の報告書を示す。
血中抗体価 報告書 氏名 ○○○○
測定方法 検査結果 病院実習の基準を満たす陽性 単 位
麻疹 (IgG-EIA法) 20.4 (≧16.0)
風疹 (IgG-EIA法) 10.0 (≧8.0)
水痘 (IgG-EIA法) 6.4 (≧4.0)
流行性耳下腺炎 (IgG-EIA法) 陽 性 陽 性
B型肝炎 (CLIA法) 4.8 (≧10.0) mIU/mL
結核 (IGRA)* 陰 性 陰 性
*結核菌特異的全血インターフェロンγ遊離測定法
この学生の相談の際に話す内容で適切なのはどれか。
a 「BCG接種が必要です」
b 「MRワクチンの再接種が必要です」
c 「帯状疱疹になる可能性が高いです」
d 「B型肝炎ワクチンの接種状況を教えてください」
e 「流行性耳下腺炎患者の診療には参加できません」
46 その後の経過:相談に来た学生は医学部を卒業し、5年後に研修医として同じ大学病院で勤務を始めた。この研修医が平日に救急外来で勤務していたところ、54歳の男性が自転車の転倒による挫創のため来院した。初診患者でこの病院に受診歴はない。この研修医が創部の縫合処置を行っている最中、誤って縫合針を自分の指に刺した。研修医は創部から血を絞り出し流水で十分に洗浄すると同時に、直ちに研修医自身と患者の血液検査を行った。
外傷患者の血液検査結果が陽性だった場合、できるだけ早期に研修医に対する内服予防投与の開始が必要なのはどれか。
a HIV
b HBV
c HCV
d 梅毒
e HTLV-1
47 次の文を読み、以下の問いに答えよ。
48歳の男性。倦怠感と口渇を主訴に来院した。
現病歴:2年前から糖尿病を指摘されていたが医療機関を受診していなかった。3か月前から倦怠感、体重減少および口渇が出現した。ここ数日で口渇が顕著になったため来院した。
既往歴:特記すべきことはない。
生活歴:会社員で1人暮らし。喫煙歴は15本/日を28年間。36歳から禁酒している。朝食は菓子パン、昼食は社内食堂の定食、夕食はコンビニエンスストアのお惣菜などの食生活である。
家族歴:父が72歳の時に膵癌。母が脂質異常症。
現 症:意識は清明。身長174cm、体重90kg。体温36.8℃。脈拍80/分、整。血圧126/88mmHg。呼吸数24/分。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない。口腔内の乾燥を認める。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。アキレス腱反射の低下を認める。
検査所見:尿所見:蛋白1+、糖4+、ケトン体4+、潜血(−)。血液所見:赤血球478万、Hb 15.4g/dL、Ht 35%、白血球9,800、血小板15万。血液生化学所見:総蛋白7.1g/dL、AST 29U/L、ALT 54U/L、LD 214U/L(基準120〜245)、γ-GT 173U/L(基準8〜50)、尿素窒素12mg/dL、クレアチニン0.8mg/dL、随時血糖281mg/dL、HbA1c 10.8%(基準4.6〜6.2)、総コレステロール150mg/dL、Na 134mEq/L、K 4.2mEq/L、Cl 98mEq/L。
糖尿病と診断し治療を開始するとともに、教育入院を行うこととした。
適切なのはどれか。
a クリニカルパスの適応ではない。
b シックデイの対処方法を教育する。
c 主治医のみの判断で指導計画を行う。
d 過去に教育入院歴がないことが条件である。
e 糖尿病合併症が診断されると教育入院は中止となる。
48 血糖コントロールのためインスリン自己注射の指導を行うことになった。
適切なのはどれか。
a 自己血糖測定機器の指導も行う。
b 未使用のインスリン製剤は常温で保管する。
c 21Gの注射針を使用する。
d 注射は毎回同じ部位に行うように指導する。
e 薬剤の注入はできるだけ急速に行うように指導する。
49 次の文を読み、以下の問いに答えよ。
79歳の女性。貧血の精査のため夫に付き添われて来院した。
現病歴:2週前の健康診断の結果、1年前には正常であった血液検査に異常がみられ、精査を勧められた。自覚症状はない。
既往歴:65歳時から高血圧症で降圧薬を服用している。76歳時から変形性膝関節症のため歩行困難で車椅子で移動をしている。
生活歴:80歳の夫と2人暮らし。
家族歴:特記すべきことはない。
現 症:意識は清明。身長150cm、体重54kg。体温36.2℃。脈拍96/分、整。血圧126/80mmHg。呼吸数18/分。SpO2 98%(room air)。眼瞼結膜は貧血様である。甲状腺腫と頸部リンパ節とを触知しない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。腱反射は正常である。感覚系に異常を認めない。
検査所見:血液所見:赤血球381万、Hb 8.5g/dL、Ht 29%、白血球4,500、血小板29万。血液生化学所見:総蛋白6.9g/dL、アルブミン4.5g/dL、総ビリルビン0.4mg/dL、AST 24U/L、ALT 22U/L、LD 163U/L(基準120〜245)、ALP 146U/L(基準115〜359)、尿素窒素11mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL、血糖93mg/dL。
病状説明を行い、診断のために翌日の下部消化管内視鏡検査を勧めたところ、患者から一言目に「検査は受けたくありません」と返答があった。
この時点でふさわしい医師の言葉はどれか。
a 「検査を中止しましょう」
b 「検査は危険なものではありません」
c 「ご家族の意見を聞いてみましょう」
d 「検査の必要性がわかっていませんね」
e 「なぜ検査を受けたくないのか、お聞かせください」
50 その後、患者は下部内視鏡検査を受け早期大腸癌が認められた。加療のため4床室に入院した。治療に関する説明のため医師が病室を訪れると、患者はベッドを起こした状態で、そばの椅子に座っている夫と話していた。4床室は満床で、空いている椅子は見当たらない。
医師から病状説明を行う際に望ましい方法はどれか。
a 夫だけを別室に呼んで座って話す。
b 患者のベッドサイドに立って話す。
c 患者の足側のベッドの上に座って話す。
d 椅子を持ってきて患者のベッドサイドに座って話す。
e 患者を車椅子に乗せ、夫と一緒に車椅子で別室に移動して話す。